『ジャイアント・キリングになれ』
1993年にユネスコ世界遺産に登録された姫路城。その姫路城のお膝元に今回取材するAC播磨イーグレッツ運営事務局があります。
バスケットボールチームとフットサルチームの2本柱で地域リーグに所属。
姫路で唯一の女子フットサルチーム。イーグレッツのイーグレットegretは、白鷺という意味。
真っ白な漆喰の壁が美しい姫路城は、まるで天を舞う白鷺のように見えるということで、別名白鷺城とも言われています。その白鷺にちなんでチーム名が誕生。天高く羽ばたくべく、日々練習に励んでいます。
その白鷺女子のチーム活動を支えているのが岡田代表。
20代でイベント音響関係の会社を立ち上げて現在58歳。
バスケットボール経験者で、家族も野球、バスケに打ち込んでいるスポーツ一家。
2012年に女子サッカーチーム「ASハリマアルビオン」を、翌年にバスケットチームを立ち上げそのオーナーに就任。ちょうどその頃、インカレベスト4に入る実力者で日体大卒業後、姫路の日ノ本短大に在籍中でもあった小平キャプテンが、フットサルも是非設立して欲しいという要望を受けて誕生したのがフットサルチーム。「日本一を目指すには、まずは「日本一を決める試合に出られるようにならないといけない。」と岡田代表。
「彼女達はポテンシャルがあるのですから、もっと果敢に試合を攻めて欲しいですね。でも、尻込みして守りに入ろうとする時もあり、歯がゆく感じます。」
代表が悔しそうに話されるのには理由があります。それは取材日の直前に先月(6月)に行われた試合結果。

普段は選手に直接指導をしないという代表ですが、その時は、思いを抑えきれずに「遠方から応援に来てくださった親御さんやスポンサー各社の方も応援に駆けつけて下さった。
他にも多くの方に支えられてフットサルが出来ている。そのことに本当に感謝しなければならない。
それに答えるには、勝つこと、一生懸命にやっている姿を見ていただくことである」と、熱く選手に伝えたそうです。
もどかしくても、歯がゆくても、常に選手達の『日本一になりたい』夢の実現に向け、選手の住むところ、働く会社も斡旋。

—笠原「なかなか仕事も紹介してくれるところは少ないですよね。苦労があるのではないでしょうか。」
—岡田代表「そうですね。せっかく紹介しても仕事の方が続かなかったりする選手もいますし、しっかりとバランスのいい食事を心がけるように言っていますが、彼女たちはまだまだ若いですからつい食費を削ってしまうんですよね。アスリートは体が基本ですからしっかりと食べて欲しいので、たまに焼肉に連れていったりします。」
―笠原「ほぼボランティアでやっているサポートですが、そこまでされる代表の思いは何ですか?」
―岡田代表「沢山の苦労をしても、試合に勝った瞬間というのは、何とも言えず嬉しいものです。その瞬間が忘れられず、その瞬間の為に彼女たちのサポートをやっているという感じです。」やはりとても嬉しいとガッツポーズをとられて言われた岡田代表。
何としても日本一を決める試合会場に出場させてやりたいという親心のようなものが苦労してもサポートし続ける原動力となっています。
その原動力こそが、代表と彼女達との絆の核であると感じました。
事務所での取材の後は、近くの体育館に移動。
雨の降りしきる午後7時にJA体育館の扉を開けると、既に仕事を終えたフットサル女子5人がウォーミングアップ。
今春ユニフォームの打ち合わせに来社した際に『日本一を目指します!』と力強く言われた小平キャプテンの姿もあります。彼女達の出身地は様々。
北海道、東京、大阪、佐賀と、全国から集まっており、ほぼ毎日仕事が終わってから練習に励んでいます。

—ウェアサプライヤーとしての絆工房に期待するものとは?
—岡田代表「是非、試合会場に応援にきて下さい。選手のモチベーションがあがって張り切りますよ。それから、手足の長い選手のユニフォームの他にも、背の低い選手用の丈の短いパンツも欲しいですね。体育館でスライディングしても破れないソックスも欲しいです。」
今回実際に取材してみて、選手の生の声も頂くことが出来、今後の商品開発に活かしたいと思います。

インタビュー記事
男前小平キャプテンにインタビューしました!
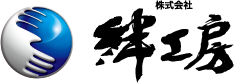
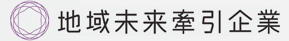




































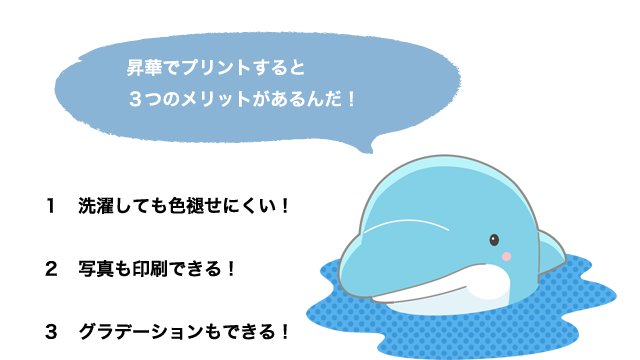
























 そして、今回の「おっとろっしゃ」だけでなく、
そして、今回の「おっとろっしゃ」だけでなく、

