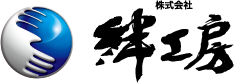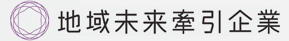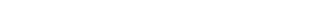神鍋高原中部に位置するブランコのある「ログリゾートかんなべ」
ログハウスの周りに咲いた花々がさわやかな秋風に揺れています。
オーナーの今村様と絆工房との出会いは約3年前に遡ります。
元絆スタッフであった藤原さんにひまわりのタペストリーの製作を依頼したのがきっかけ。
その後、豊岡市商工会が主催する経営者対象のおひねり経営勉強会「本当に楽しんで儲けることができる方法がある ワクワク系マーケティングから学ぶ」(講師は笠原支部長)という広告に目が留まり「楽して儲けられるなんて!」と即参加。
結果、「もう〜楽などころか苦しいやん!(笑)」。
とてもお話しが上手なので、ペンションオーナーに至るまでの経緯を伺ったところ、納得の笑顔、納得の会話力の理由が判明しました!

■”大阪で美人の所長がいる店舗”と評判になったトップセールス・ウーマン

3人姉妹の末っ子でお嬢様としてのんびり育った今村さん。
お姉さん達が経営するブティックを手伝うという道もありましたが、何かもっと違うことがしたいと学校卒業間近の2月に就職活動を開始し、大手製薬会社の採用試験を受験。
見事、一番で合格し、女性の花形職種である受付嬢として働きます。
その後結婚し、主婦として母として忙しい日々を送っていましたが、三十二歳の時に大手保険会社に就職。
そこで持ち前の明るさと巧みな話術で人を惹きつけ、あっという間にトップセールス・ウーマン。
店舗一つを任されるまでになり、「大阪で美人所長がいる店舗」と評判になります。
57歳の時には、営業職から若手の教育指導を担当。
「10年は1つの会社で働いてみること」
「何でもトップになってみようという心意気が大事」
「人の三倍は働くこと(時間ではなく)」
「人がしていること以上のことをしてみること」等、長年トップセールス・ウーマンとして走り続けて培った自信に満ちた言葉の数々は、仕事以外にも通じる格言です。
”トップセールスマンには、共通の言動なり習慣がある”と言われることがありますが、弁舌さわやかに話す今村さんもまさに、引きの営業力を知ってる方です。
「保険の話なんてしなくても契約はとれます。」ときっぱり。
それは、売り上げにならなくても顧客のためにさらには顧客の周りにいる人にも何ができるか、何が喜んでくれるかを常に考えて仕事をされたそうです。
前回のヘルメース上田社長さんの「仕事は自分でつくりだすもの、動くもの」に通じるものがあります。

■カナダ産ログハウスに溶け込む日本の絵画

12年前に前オーナーから引き継いだ『ログリゾートかんなべ』は、オールカナダ産の木で作られたログハウス。
広々としたリビングで一際目を引くのが横に延びた太い柱。
その見事なカービングの技は、今はもう日本には100人ほどしかいない宮大工さんが作られたそうです。
また、ログハウスの随所に飾ってある絵画は今村さんの自作。
「1つのことに10年は続けてみる」という言葉通り、学生時代から日本画を学び、今も指導を受けている絵画は、趣味を越えたものです。四季折々の花々を和紙に描かれたということで、ログハウス全体がしっとりした落ち着いた雰囲気に包まれています。
絵画の他にも、ゴルフ、書道、ガーデニング、陶芸、ジャズ、全て10年以上続けておられるそうで、それらが今村さんの人生を色鮮やかにかつ活動的にしています。

■「遊ぶことだけの人生は送りたくない」
保険会社を定年退職した後は、今村さんの家族は悠々自適の生活を送ると思っていたそうですが、それを見事に裏切ってのペンション経営。
住み慣れた大阪から単身神鍋に移住します。
「家族には事後報告!だって遊ぶだけの人生を過ごしたくないわ。」
「40代の時に、”21世紀の私”という夢を書いたんです。その時にホテル経営って書いたの。ホテルではないけれど、ペンション経営しているんだから、何だか不思議よね。経営に、趣味の活動に忙しいけれど楽しいわ。」
1日5組ほどの少ないお客様との絆を大切にしている『ログリゾートかんなべ』。
「ここをコミュニケーションの場にしてほしい」と言われるように、自然との絆、仲間との絆を大切にしています。
人が多い都会から来られたお客さんにゆったりとした時間をここ神鍋で過ごしてもらいたいと、あえて客数を少なくしています。
ピアノもあり、プロ並みの歌唱力を持つ今村さんのジャズが聴けるかも知れません。
神鍋の自然を背景に、但馬牛のバーベキューを楽しめるウッドデッキもあります。

『ログリゾートかんなべ』で仲間との会話はもちろん、軽快なテンポで話しをされる美人オーナー今村さんの会話も楽しんでみて下さい。
取材日も、今村さんの話術に吸い込まれるように聞き入ってしまい取材時間が大幅にオーバー。
それでも、「もう終わり?まだ話したいのに。」
ここは、都会の人だけでなく、訪れる人皆さんの心も体も元気にしてくれます。